配管系の耐震設計
エネルギー吸収能力と変位吸収能力
耐震設計の目的が地震災害のリスクの軽減にあることはいうまでもありません。兵庫県南部地震の経験を教訓に、漏洩がなければ塑性変形はあってもよいとして、発生確率の非常に小さい破壊的地震まで想定するようになりました。破壊的地震を想定し、塑性変形を許容する設計を行うには、配管のエネルギー吸収能力、変位吸収能力に関する知識が必要となります。概念だけでも理解しますと、過去の地震で配管がなぜ壊れたのか、なぜ壊れなかったのかが理解でき、塑性変形を許容した耐震設計ではどんなことに注意しなければならないかが分かるようになります。弾性設計に慣れた配管設計者には馴染みにくいかもしれませんが、大切なことですので最初に説明したいと思います。
■鋼管のエネルギー吸収能力と変位吸収能力
● 鋼管の力−変形曲線
鋼管の一端を固定し、自由端に力を加えていきますと、力に比例して変位が大きくなっていきます。やがて固定端の最外縁が降伏し始めます。このときのモーメントを降伏モーメントといいます。さらに力を加えていきますと全断面が降伏します。このときのモーメントを全塑性モーメントといいます。固定端における曲げモーメントが全塑性モーメントを越えるようになりますと、力と変形の関係は非線形になり、変形量が増大し始めます。そのまま力を加え続けますと、固定端に近い部位で座屈が始まり、暫くして当該部位に亀裂が発生します。力と距離の積はエネルギーですから、配管は亀裂が発生するまでに、力−変形曲線が囲む部分の面積分のエネルギーを吸収したことになります。つまり、自由端から加わる力に対し、鋼管はこれだけのエネルギー吸収能力を有していることになります。亀裂が発生したときの変形量は、自由端に変位を加えられた場合の変位吸収能力を表しています。
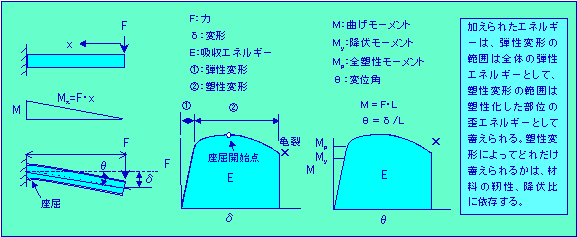
配管が破壊的地震に襲われますと、慣性力として、あるいは相対変位によって地震のエネルギーが繰り返し入ってきます。配管に入ってくる地震のエネルギーの総量が配管のエネルギー吸収能力を超えなければ、塑性変形は残るものの、亀裂の発生には至らないことになります。実際の配管系はもっと複雑で、慣性力については振動モードごとに、また相対変位については方向ごとにエネルギー吸収を負担する部位は違ってきますが、基本概念としてはこのようなものとなります。
●直径―板厚比の影響
座屈がいつ始まるかは鋼管の直径―板厚比によって変わり、この比が大きいほど小さな角度で始まります。この比がある程度小さくなりますと座屈しなくなり、固定端の応力が引張強さに達するまで塑性変形が進行するようになります。
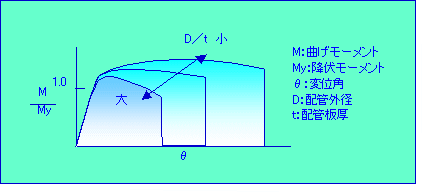
一般の小口径配管は直径−板厚比が十分小さく、座屈しませんから、直管部の長さに応じ、配管の塑性変形だけで大きな相対変位を吸収することができます。一方、直径―板厚比の大きい鋼管は比較的小さい変位角で座屈してしまいますので、塑性変形だけで相対変位を吸収するには限界があります。この問題を解決してくれるのが、後で述べるエルボの変形特性です。
●脆弱部の影響
配管の固定端近傍に直管部よりも強度の低い部位があると、配管本来のエネルギー吸収能力、変位吸収能力が発揮される前に、当該部位で破断してしまいます。このような部位、配管要素としては、溶接効率の低い溶接継手、ねじ込み継手、フランジ継手、鋳鉄弁などが挙げられます。実際の地震被害も、こうしたところに集中しています。座屈しない小口径管といえども、固定端近傍にこうした部位があれば注意が必要です。
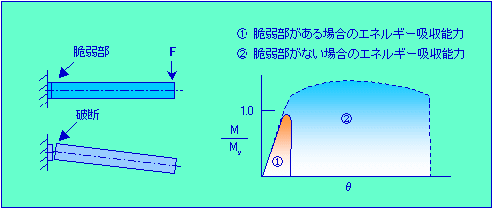
■エルボ付き鋼管のエネルギー吸収能力と変位吸収能力
エルボ付き鋼管のエネルギー吸収能力
鋼製のエルボに曲げモーメントを加えますと、梁として計算したときに比べて大きな角変位が得られます。この比のことをフレキシビリティファクターと呼び、配管系の熱膨張解析などで用いられてきています。エルボに曲げモーメントを加え続けますと、曲げモーメントと変位角の関係は非線形となり、直管の降伏モーメントよりも小さな曲げモーメントで角変位が進行するようになります。 塑性化の領域を拡げてはいきますが、最大歪はなかなか亀裂に至るレベルに達しません。このような特性を持ったエルボを鋼管の固定端側に取り付け、自由端に力を加えていきますと、直管部が座屈せずに塑性変形が進行し、継手への負担も軽くなります。この曲げモーメント低減効果は、直径―板厚比が大きいエルボほど大きくなります。
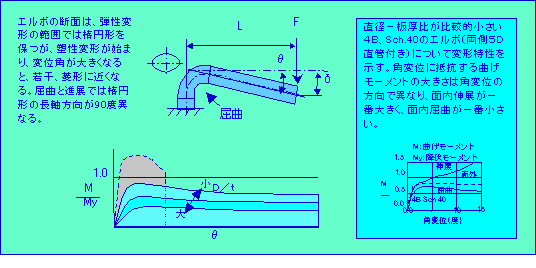
このような効果はエルボの断面が楕円化することによるものであり、差込溶接、ねじ込み継手、塩ビ管のエルボにはみられないものです。突合せ溶接のエルボでも、直径−板厚比が小さいものや、直管部に比べて板厚が過剰に厚いもの(例えば1.5倍)も、このような効果は期待できません。また、鋼管のエルボでも角変位が大きくなりますと断面形状が塑性変形し(楕円形から菱形に近くなる)、逆向きの角変位に対してこれが影響しますので、繰り返しに対しては弱くなります。
●地盤変状に基づく相対変位の吸収
大規模な地盤変状が起きますと、数10cmを越え、1mに達するような、非常に大きな相対変位が配管系に加わることがあります。このように大きな相対変位を弾性変形だけで吸収しようとすると広いエリアを必要としますが、繰り返しがありませんので、エルボの変形特性を利用することにより比較的狭いエリア吸収することができます。
配管系に大きな相対変位が加わりますと、初めは弾性変形だけで吸収していきます。そのうちに一点が降伏して塑性ヒンジ(曲げモーメントはゼロではないので完全なヒンジではない)が形成され、曲げモーメントの分布が変わってきます。相対変位がさらに加わっていきますと別の点が降伏し、その点も塑性ヒンジを形成するようになります。2つの塑性ヒンジを結ぶ直線(塑性ヒンジの間は直管とは限らず、途中に曲がりがある場合もある)が相対変位の方向とずれていますと、その区間がリンク機構を成し、当該区間だけで相対変位が吸収されていくようになります。相対変位の吸収量が大きくなってきますと、相対変位に直角な方向に新たな相対変位が生じ、これが弾性変形の限界を超えますと別の点が降伏し、新たな塑性ヒンジが形成されるようになります。
降伏して塑性ヒンジが形成されるのは一般に直管の支持部またはエルボ部ですが、直管部の座屈は亀裂が入る恐れがありますから、設計ではエルボ部だけが降伏していくような構造を考えることになります。少しややこしいので、簡単な形状をした配管について説明しておくことにします。
●Z型配管
Z型配管の場合、相対変位に対して2つのエルボ部が順に降伏して塑性ヒンジを形成しますので、塑性変形が円滑に進行し、無理なく大きな相対変位を吸収することができます。許容される塑性歪に対応する変位角まで期待できますが、相対変位の吸収量が大きくなるにつれてエルボが挟む直管の軸方向収縮量{L(1-cosθ)}が次第に大きくなりますので、これを吸収する可撓性が必要になってきます。L1、L3が共に短い場合は注意が必要となります。
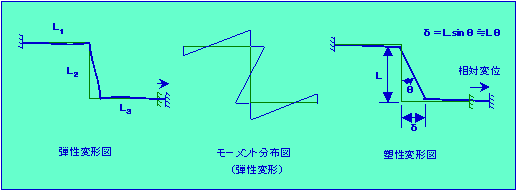
●立体Z型配管
立体Z 型配管の場合は、一方のエルボは面内伸展、もう一方のエルボは面外ねじれで相対変位を吸収していきます。L1の距離が長いと、エルボ部よりも固定端が先に降伏し、座屈する恐れが出てまいります。このような場合、エルボに近いところで相対変位の方向の移動を拘束すれば、固定端が座屈することなくエルボ部が降伏し、塑性変形が円滑に進行するようになります。エルボが挟む直管の軸方向収縮量に注意が必要なのはZ型配管の場合に同じです。
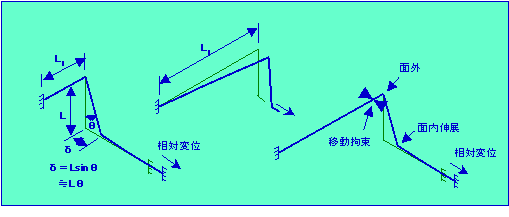
●コの字ループ付き配管
コの字ループ付き配管は2つのZ型配管の組み合わせとなります。引張方向、つまりエルボが伸展する方向に相対変位が作用した場合には、両側でエルボが順次降伏し、ほぼ均等に塑性変形が進行します。圧縮方向、つまりエルボが屈曲する方向に相対変位が作用した場合には、変形曲線がピークに達するまでは両側でほぼ均等に塑性変形が進行し、ピークに達してからは片側(最初にピークに達した側)だけで進行するようになります。相対変位に直角な方向の変位は拘束されませんので、相対変位の吸収量が大きくてもZ型配管におけるような固定端への影響はありません。地盤変状が起きた場合、基礎は護岸方向に移動し、移動量は護岸に近いほど大きくなりますので、一般には引張方向の相対変位となります。
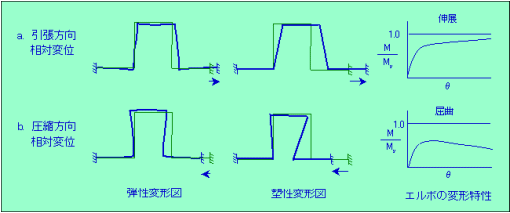
地盤変状に対する構造設計の具体例は、配管系の耐震設計・耐震診断≫地震による影響の軽減≫地震による影響の軽減例でも説明します。
